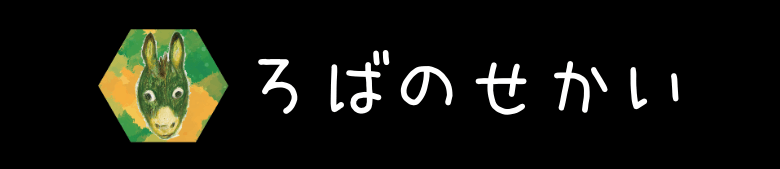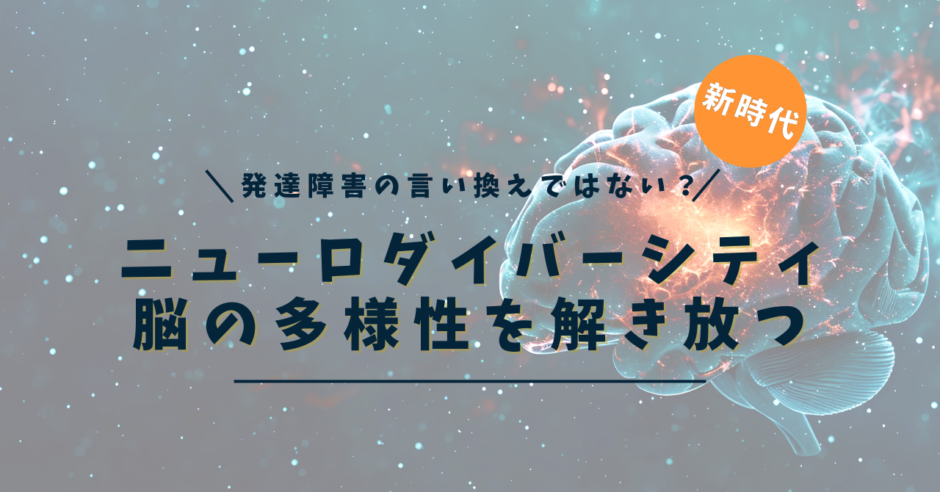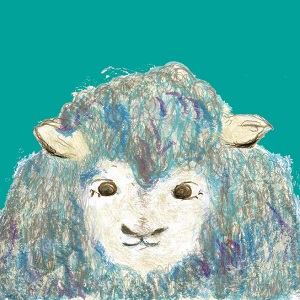
今回のテーマはニューロダイバシティです!

脳も多様性を見出す時代なのです!
「普通」って、なんでしょうか?辞書的な意味合いでは、他と特に異なる性質を持ってはいないさまとされ、一般的や平均的が類語としてはあります。
社会に合わせ、学校に合わせ、職場に合わせること。僕たちは「こうあるべき」という「普通の型」に自分を当てはめようとする生き物です。
でも、その「普通」に適応できないと感じたとき、あなたは自分を責めたことはありませんか?
昨今、日本でもよく耳にするようになってきたこのニューロダイバシティという考え方。
この記事では、「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」という考え方を通じて、 「普通」という幻想をそっとほどきながら、「自分はこのままでいいんだ」と思える視点をやさしくお届けします。めちゃくちゃ長いのでゆっくり時間のある時に読んでくださいな。
- ニューロダイバシティについて知りたい人
- 「発達障害」「グレーゾーン」という言葉に興味を持つ人
- 枠を超えた変化を見出す人
目次
- 1.普通って誰が決めた?ニューロダイバーシティから見る神経多様性の本質
- 2. ニューロダイバーシティとは?発達障害の言い換えではない理由と多様性の本質
- 3. ニューロダイバージェントの定義とは?支援か、特性か、揺れる視点の現在地
- 4. 「みんなが同じ」社会の限界。ニューロユニバーサリティが奪う自由
- 5.障害は誰がつくる?社会が生きづらさを生み出すメカニズム
- 6. ラベルに縛られないために。診断名は取扱説明書であってもいい
- 7. 「支援=特別」じゃない。社会全体をアップデートする視点
- 8. 人間は似ていなくて当たり前。ニューロダイバーシティの原点に還る
- 9. ニューロダイバーシティ的に生きるとは? あなたの違いが強みになる瞬間
- 10. あなたの“普通”を再定義する。 違いを愛するという生き方
- 11. もっと学びたい人へ|ニューロダイバーシティおすすめ本とサイト
1.普通って誰が決めた?ニューロダイバーシティから見る神経多様性の本質
僕がこの問いに初めて向き合ったのは、あるクライアントとのセッションの中でした。
「自分は普通じゃないんです。だから、どこに行っても浮いてしまうんです。」
そのつぶやきを聞いたとき、僕はこれは、彼だけの悩みではなく、誰しも遭遇する可能性のある状況だと感じました。
学校でも、会社でも、家庭でも。 「みんなと同じようにできること」が評価されて、 「みんなと違うこと」は、ときに「問題」や「障害」とみなされます。
でも、ちょっと冷静になって考えてみてほしいのです。
もしこの世界に、「全員が同じ」だったら、どうなるでしょうか?
「目を見て話せない」「朝が苦手」「人と雑談するのが苦手」── そうした違いが、なぜ「不適応」と呼ばれやすい性質をもつ社会に僕らはいるのでしょうか?
もし、あなたが「普通」に適応できないとしたら、それはあなたのせいではないかもしれません。 社会や時代のほうが、まだ「アップデート途中」なだけかもしれないのです。
そんな視点の転換の入り口として、 「普通って何だろう?」「僕たちはなぜ、普通でいようとするのか?」 という問いを一緒に見つめ直していきましょう。
「普通」という幻想を問い直す
そもそも、「普通」ってなんなのでしょう?
そう聞かれて、明確に答えられる人はどれくらいいるでしょうか。
たとえば、100年前の日本では、左利きは「矯正」の対象でした。 箸を右手で持たなければ怒られ、文字を左で書くこともNGとされていた時代があったのです。
でも、今ではそれを「障害」だという人はいませんよね。
このように、「普通」という概念は、時代や文化、社会システムによって簡単に変遷や変化を経験していくものです。
つまり、いま「普通じゃない」とされているものも、 10年後には「個性」や「特性」として歓迎されている可能性はあります。はたまた10年なんて待たずとも、環境によって明日にでも変わる可能性さえあります。
あなたの「生きづらさ」が、社会の歪みを映している
「普通の学校」「普通の働き方」「普通の人間関係」 それらに適応できないと感じるとき、僕たちは「何かが自分が欠けている」と思い込みがちです。そしてそれは至ってフツウの心理です。
でも、それって本当に「あなたのせい」なのでしょうか?
- 「みんなと同じペースで勉強できない」
- 「朝が苦手で出勤がつらい」
- 「雑談や飲み会がどうしても苦手」
- 「特定の作業が難しいと感じる」
そうした「生きづらさ」は、実は「社会の設計」が、特定の脳のタイプに合わせて作られてきた結果かもしれません。
あなたの違和感は、「あなたが壊れている証拠」ではなく、「社会がまだ進化の途中」というサインかもしれないのです。ニューロダイバーシティの出発点は、 「あなたの感じている違和感には、ちゃんと意味がある」 という認識から始まります。
そしてそれは、あなたの生き方にも、社会の未来にも、新しい可能性を開いてくれるはずです。
- 「普通」の概念は時代や文化によって変化する
- 「生きづらさ」は社会(及び環境)の設計が合っていないサインかもしれない
- 違和感には意味があり、社会の未来に可能性を開く。
2. ニューロダイバーシティとは?発達障害の言い換えではない理由と多様性の本質
「脳の多様性」は、すべての人間に当てはまる話
「ニューロダイバーシティって、発達障害のやさしい言い換えでしょ?」と思っていた方もいるかもしれません。 実際、そう語られる場面も増えてきました。
後述しますが、企業はND(ニューロダイバシティ)採用・ND人材などの用語を使い始め、SNSでニューロダイバシティやダイバージェントとは、「発達障害などを”障害”という視点ではなく、脳や神経の多様性と捉えようとする動きです!」と発信する内容も増えてきていきます。
その背景には、発達障害という言葉に対する スティグマ(否定的なイメージ)や、「診断名がある人だけが困っている」という誤った認識が根強くあるのかもしれません。
でも、この言葉の背景には、もっと深い「視点の転換」が込められていると個人的には思っています。
ニューロダイバーシティ(Neurodiversity)=神経多様性とは、「脳の働き方には多様性がある」という考え方です。
最近では、「ニューロダイバーシティ=発達障害の新しい言い方」と誤解されることがありますが、これは本質とは少し違います。
ニューロダイバーシティは、本来「すべての人間に当てはまる」視点です。
たとえば
記憶力が抜群な人もいれば、直感でひらめくのが得意な人もいる。計画を立ててコツコツ進めるのが得意な人もいれば、衝動的に動くことで力を発揮する人もいる。
一つのことに深く集中できる人もいれば、マルチタスクが得意な人もいる、
雑音があると集中できない人もいれば、カフェのざわめきの中で逆に集中できる人もいます。 朝型が得意な人もいれば、夜になってからエンジンがかかる人もいる。
こうした違いは、「発達障害の有無」とは関係ありません。 診断されていなくても、誰もが脳のユニークな動きを持っているのです。
たとえば、衝動的に動くタイプの人は、予測不可能な場面でとっさに決断できる力を持っています。 一つのことに没頭できる人は、専門性の高い分野で才能を発揮しやすいのです。
「神経多様性」とは、こうした“違い”を「欠陥」ではなく「前提」として認める考え方なのです。
「普通」の基準は、いつ、誰が作ったのか?
では、なぜ僕たちは「普通でいなければ」と思い込んでしまうのでしょうか?
実は、その“ふつう”という基準は、歴史の中でつくられてきたものなのです。
たとえば、18〜19世紀の産業革命以降、社会は「工場労働」に適した人材を求めるようになりました。
- 朝決まった時間に起きるのが当たり前
- 指示通りに動くことが正しい
- 同じペースで学び、同じ行動をとることが評価される
これらの価値観は、「効率と均一性」を重んじる時代に必要だった教育と労働の型だったのです。そして、それは良いことでも悪いことでもなく、言ってしまえばただそうだった。というものです。
でも、それは「全員がそうあるべき」という意味ではなかったはずです。 もともと人間は、そんなに均一な存在ではないのだから。そうだとしたらつまらんですし。
「普通」よりも「多様性」が強みになる時代へ
今、私たちの働き方や生き方は大きく変わり始めています。
- リモートワーク
- フレックスタイム
- 副業・フリーランス
横文字多めではありますが、かつては「例外」とされた働き方が、今では“ふつう”になりつつあります。
それなのに、心のどこかでまだこう思ってしまうことはありませんか?
- 「9時〜17時に働けない自分は怠けているのでは?」
- 「人の目を見て話せない自分は、社会性がないのでは?」
- 「みんなと同じペースで動けないのは、自分のせいでは?」
でも、その「不安」の正体は、古い「当たり前」に縛られているだけかもしれません。
もしかするとそれは、すでに社会のほうが先に変わり始めているサインであり、あなたの“違和感”こそが、新しい時代への入り口かもしれません。
社会が変わっているのなら、僕たちの「普通」の概念も、そろそろ変わるときだと思います。昭和の古臭いと揶揄されるようにね。
ニューロダイバーシティという定義は、「発達障害を含むすべての脳の多様性」を尊重する考え方です。 それは、「生きづらさ=本人の問題」ではなく、「環境と合っていないだけかもしれない」という視点でもあります。
たとえば、静かな場所で集中できる人には在宅ワークや図書館が合うかもしれません。 逆に、人との雑談から発想が広がる人には、オープンスペースやカフェのような環境が刺激になります。
もし今の働き方や学び方がしっくりこないなら、それはあなたが間違っているからではありません。 「どんな環境なら、自分の脳が心地よく動くのか?自分らしくいることに許可が与えられるのか?」そんな問いを、自分に向けてみる時期なのかもしれません。
誰かに合わせるばかりの毎日がしんどいなら、もしかしたらそれ“違っていていいサインという可能性さえあります。
ニューロダイバーシティは、「一部の人のため」ではなく、 すべての人が“自分らしい脳の使い方”で生きていいんだよという、大切なメッセージだと個人的に思っています。
だからこそ、「自分の脳に合った生き方を選ぶこと」が、これからの時代の新しい「あたりまえ」の新基準になるのかもしれません。
- ニューロダイバーシティは「脳の多様性」を尊重する考え方。
- 「普通」の基準は歴史的に作られたもので、変化している。
- 自分の脳に合った生き方を選ぶことが大切。
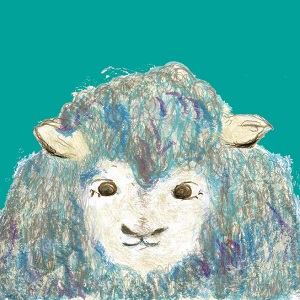
こんなキレイごと並べられても!という気持ちを胸ポケットにしまいながら続きを読んでくださいね!
3. ニューロダイバージェントの定義とは?支援か、特性か、揺れる視点の現在地
ニューロダイバージェントの定義の変遷
「ニューロダイバージェント(Neurodivergent)」という言葉は、1990年代にオーストラリアの自閉症活動家ジュディ・シンガーが提唱した「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」という思想から生まれました。
当初は、自閉症やADHD、学習障害など、生まれつき脳の発達が「典型的(ニューロティピカル)」とは異なる人々を指していました。
しかし近年では、その定義が拡張されつつあります。
- うつ病、不安障害、双極性障害、統合失調症、強迫性障害(OCD)などの精神疾患
- トゥレット症候群、摂食障害、感覚処理の違いを持つ人々
さらに、HSPやディスレクシア(学習障害の1つ)なども含まれます。このように、「脳の働きが社会の典型から外れる状態」を広く含める考え方が、少しずつ広まり始めているのです。
ただし、どこまでを含めるかは個人やコミュニティによって異なり、精神疾患を含めることに慎重な立場もあります。
視点の違いが生む、世界の見え方の変化
ここで注目したいのは、「ニューロダイバージェント」という言葉が持つ視点によって、世界の見え方そのものが変わってしまうということです。僕は4つの視点が生まれると思っています。
A.「多様性≒障害」として捉える視点
たとえば「聴覚障害」という言葉には、「聞こえないこと=不便で、補わなければならないもの」という前提が含まれがちです。
- 社会(健常者基準)に適応することが前提になる
- 補聴器や字幕といった「支援」が必要とされる
この視点では、「どうやって社会に合わせるか」が主軸になります。
B.「多様性≒特性」として捉える視点
一方で、「耳が聞こえない人」という言い方をすると、
- 「聞こえない」という状態を前提に、その人の人生をどう創っていくか
- 聴覚以外の感覚の鋭さや、手話文化の豊かさに目が向く
この視点では、軸は「社会」から「その人自身」へと移っていきます。
ニューロダイバージェントも、この視点のズレの中で揺れている概念のようにとらえています。
従来の視点(哲学的なアプローチ)
- 人間の脳は本来、多様である
- 違っていて当然、それが自然な姿
- 社会が違いに合わせて進化するべき
- 本質は「多様性の肯定」
本来のニューロダイバシティは、こちらの文脈がメインです。
最近の視点(支援・制度的アプローチ)
一方で、昨今は以下のような視点がメインになります。
- ニューロダイバージェント=発達障害や精神疾患のある人
- 診断、治療、支援制度などが話題の中心になる
- 社会の基準に「どう合わせていくか」が主なテーマ
こうして、「社会を変える」から「個人が適応する」へと、言葉の意味が少しずつスライドしてきているのです。この言葉の意味のスライドによって微妙なひずみが生じていると感じています。
融合という希望──「支援」と「自己受容」の共
この揺れのなかで、僕が希望を感じているのが「融合」という視点です。
- 支援を受けながら、自分の特性を受け入れ、活かしていく
- 社会への適応手段としてだけでなく、自分らしく生きるための“土台”として支援を捉える
たとえば、
僕の息子は、重度の聴覚障害をもっています。彼には、聴覚障害によくみられるADDやADHD傾向(のグレーゾーン)もありました。
数年前まで彼は聾学校に通っていました。そこでは、「障害」として捉える視点が強く、いかに健常者に近づくか、いかに遅れを取らないかが教育の軸でした。ひらがなを早めに覚えさせるといった、認知的なトレーニングが重視されていたのです。
でも、そのやり方が息子には合いませんでした。次第にお腹が痛くなり、物理的に学校に行けなくなってしまったのです。
そこで彼は、市立の保育園に通うことになりました。保育園では、言葉の遅れよりも、彼自身が何を感じ、どう遊びたいのかに寄り添ってくれる大人たちがいました。
結果として、発語や言語理解の面では、同年代と比べて遅れている部分もあります。でもその一方で、自発性や感情表現の豊かさ、「楽しむ力」やお友達との非言語的なコミュニケーション能力など、言葉では測れない心の発達が大きく育ったのです。
保育園の先生も、通っているリハビリの先生も、「ここまで心が育っているのは驚き」と言ってくれました。
もちろん、すべてが順風満帆というわけではありません。まだ課題もあります。でも僕は、彼にとって「支援」と「自由な成長」がどちらも必要だったのだと、今なら思えます。
それは例えば、視力が弱い人がメガネをかけて自分らしく暮らすように
ADHDの人が、アイデア力や瞬発力を活かしながら、スケジュール管理はツールで補うように
このように、「支援 × 自己理解 × 活躍」が共存している状態こそ、 現実的でありながら、人を前向きにするニューロダイバージェントのあり方だと思っています。
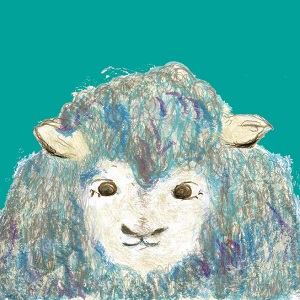
めちゃくちゃ乱暴に要約するなら「バランス」です!
融合の価値とは?
- 自己否定につながらない:「治す」ではなく「活かす」という視点に立てる
- 社会とつながりやすくなる:支援を受けながらも、自分のやり方で協働できる
- 活躍の幅が広がる:自分の特性を理解し、強みに変える環境を選べる
支援はあくまで補助的な道具であり、主役はいつだってその人自身です。
要するに、「融合」とはバランスなのだと思います。
社会に合わせるだけでも苦しくなるし、自分らしさだけを貫こうとしても、やっぱりどこかで生きづらさが残ってしまう。だからこそ、必要な支援を受けながら、自分の特性を大切にしていく。その“ちょうどいいバランス”を、自分の体験を通して見つけていくことが大事なんだと思います。
このバランスは、制度が決めてくれるものでも、誰かが教えてくれるものでもありません。本人が「これなら息がしやすい」「これなら楽しい」と感じる場所を探っていく、小さな実験の繰り返しの中で見えてくるものです。
そしてその過程こそが、ニューロダイバージェントという言葉が本来持っていた、“違いを肯定する”という哲学の延長線上にあるのではないでしょうか。
この「融合」の視点は、 本来のニューロダイバーシティの哲学と、現実社会をつなぐ“実践的な橋*になり得ると思っています。
4. 「みんなが同じ」社会の限界。ニューロユニバーサリティが奪う自由
違いを排除した社会は、創造性も失う
もう少しニューロダイバシティの哲学を深掘りしてみます。「みんな同じ」が前提の社会を、少し想像してみてください。
- すべての人が朝型で、決まった時間に出社する
- すべての人がマルチタスクをこなせる
- すべての人が「空気を読む」ことが当たり前
一見すると、効率的で秩序のある社会に思えるかもしれません。
でも、その社会には「違い」がありません。
そして、「違いのない社会」は、やがて創造性・柔軟性・革新性を失っていきます。
創造とは、異質なものが出会い、混ざり合うことで生まれるもの。 つまり、「違い」があるからこそ、新しいアイデアも、ユニークな価値も生まれてくるのです。
画一的で“誰もが同じ”であることが前提の社会は、 見た目こそ整っていても、そこに住む人たちの息苦しさや孤独感を、じわじわと広げていきます。
「違いのない社会」は、きれいに整った檻かもしれません。
「ニューロユニバーサリティ」が生む息苦しさ
この「みんなが同じであること」を求める社会の姿は、まるでディストピア小説の世界です。
たとえばジョージ・オーウェルの小説『1984』では、個人の思考や違いが“危険”とされ、徹底的に統制されていきます。
みんなが同じ言葉を話し、同じ価値観で生き、同じ方向を向いている。
それは「整った社会」のように見えて、実は自由や創造が禁じられた檻なのです。
ここで紹介したいのが、「ニューロユニバーサリティ(Neuro-universality)」という概念です。
これは、すべての人に“同じ”神経的特性や行動様式を求める価値観を指します。
たとえば、こんな“無意識のルール”が社会にはびこっていませんか?
- 「目を見て話すのが礼儀」
- 「朝早く起きるのが正しい」
- 「協調性があることが社会性」
一見、当たり前のように思えるこれらのルールも、 実は一部の人の特性を“基準”にして作られたものにすぎません。
この“正しさ”をすべての人に強いることで、
「できない自分はダメなんだ」「人として未熟なんだ」
というように、自分を責めたり、劣等感を抱いたりする人が増えてしまうのです。
“正しさ”の裏には、「適応できなかった人を排除する構造」が潜んでいるかもしれない、という視点が今、求められています。
ニューロダイバーシティ(神経多様性)が「違いを前提にする社会」を目指す概念だとしたら、 ニューロユニバーサリティはその真逆。
- 「みんなが同じようにできる社会」を目指す
- 「できない人」に支援ではなく、矯正を求める
そんな社会では、生きやすいのはごく一部の定型の人たちだけになってしまいます。
それ以外の人は、
- 無理をして適応しようとする
- 自分を否定しながら生きる
- 自然体でいられる場所がなくなる
結果的に、その整った社会は、一部の人にとってしか機能しないものになってしまうのです。
違いがあるから、世界は面白い
僕たちが本当に目指すべき社会は、
「みんなが同じようにできること」ではなく、
「みんながそれぞれのままでいられること」ではないでしょうか?
効率性や統一性も、もちろん大切です。でも、その裏で「違い」が削られてしまうなら、社会が失うのは、ただの個性ではありません。
それは、未来の可能性です。それは、まだ見ぬ発明です。それは、あなたがもたらすかもしれない、新しい価値です。
違いは、可能性。違いは、発明のタネ。そしてなにより、違いは“あなたらしさ”です。
ニューロダイバーシティという思想は、「誰もが同じであるべき」というニューロユニバーサリティへの、明確なアンチテーゼです。
多様であることは、弱さではなく、可能性。
“標準”に合わせることではなく、“違い”を前提にした設計こそが、本当の意味で人間らしく、創造的な社会をつくっていく鍵なのだと思います。
違いがあることが前提の社会は、きっと、もっと自由で、もっとやさしくて、もっとおもしろい。
「違い」を尊重することは、社会を前進させる原動力になるのです。
5.障害は誰がつくる?社会が生きづらさを生み出すメカニズム
環境次第で「障害」は「特性」に変わる
たとえば、もしこの世界にメガネという道具が存在しなかったら、 視力が悪い人は「障害者」として扱われていたかもしれません。
でも今の時代、視力が悪くても「障害者」と見なされることはほとんどありませんよね。
それはなぜでしょうか?
答えはシンプルです。 「メガネ」というツールによって、視力の問題が支障ではなくなったからです。
つまり、「環境を補う手段」があることで、 本来は困りごとだったはずの状態が、自然な個性として扱われるようになるのです。
では、脳の特性についても同じように考えてみたらどうでしょう?
もし、社会の側に「脳の多様性」に対応する道具や仕組みが整っていたらきっと、多くの人が「障害」というラベルを貼られずにすむのかもしれません。
「あなたが困っている」のではなく、「社会が困らせている」
- 車椅子ユーザーが駅で立ち往生するのは、段差やエレベーターの不足のせい
- 聴覚障害の人が情報から取り残されるのは、字幕や手話通訳の不足のせい
- 発達特性のある人が職場で苦しむのは、一律の働き方に多様性がないから
こうした「困りごと」は、個人の中にあるのではなく、社会とのミスマッチから生まれているのです。
この視点は、「社会モデル(Social Model of Disability)」と呼ばれ、 障害を「個人の問題」としてではなく、「社会の構造の問題」として捉える考え方です。
たとえば、もし手話がこの社会の標準言語だったとしたら? 聴覚障害の人は、何も「障害者」ではなくなります。
つまり、「障害」とは、**その人に備わった性質ではなく、 社会の設計と合っていないことで生まれる“状態”**なのです。
問題があるのは“あなた”ではなく、社会の側かもしれません。
ADHDの脳は“不利”ではなく、“適応のミスマッチ”
たとえば、ADHDの人がよく指摘される特性に、こんなものがあります:
- 集中力が持続しない
- 忘れ物が多い
- 思いつきで行動する
これらは、画一的な教育現場や静かなオフィスでは“困った特性”とされがちです。
でも、少し視点を変えてみてください。
- アイデアが次々と湧き出る柔軟な発想力
- 一瞬で深く入り込む「ハイパーフォーカス」
- スピード感と直感的な判断力
こうした特性は、 変化が激しい現場や、創造性・柔軟性が求められる分野では、 他の誰にも真似できない圧倒的な武器になります。
つまり、ADHDの脳は「不利」なのではなく、 今の社会の“デフォルト設計”に合っていないだけなのです。
合わない環境では「障害」に見える。 でも、合う環境では「才能」になる。
この視点は、ADHDだけでなく、あらゆる“違い”に当てはまります。
あなたが抱える特性は、環境が変われば「強み」になる。 それは、「あなたが壊れている」のではなく、「あなたを支える設計が足りていない」だけかもしれません。
「障害」は、社会設計のアップデートで変わる
「障害」という言葉は、しばしば“固定された個人の属性”のように扱われがちです。
でも、ニューロダイバーシティの視点から見れば、 それはむしろ、**「その人にとって今の社会が生きづらいかどうか」**という、 相対的で環境依存的な概念なのです。
- メガネが視力を補うように
- スロープが移動の自由を広げるように
- 手話が文化をつなげるように
- テキストチャットや在宅勤務がコミュニケーションを補うように
社会の側が変われば、「障害」は「特性」に変わります。
人が変わる必要はない。社会のほうがアップデートされればいい。その視点が、「生きづらさ」を抱えるすべての人にとっての希望になるはずです。
そして、私たち全員が、そのアップデートに参加できる存在なのです。社会が“障害”を生み出しているなら、社会が“可能性”も生み出せる。
これは昨今の風潮の1つですよね。
「社会が変わる」だけじゃない。自分で選ぶという自由もある
もちろん、社会がもっと柔軟になれば、多くの人の「生きづらさ」は減るはずです。でも同時に、僕はこうも思います。
社会は変わっていくけれど、それを待つだけじゃなく、僕たちは「選ぶ」こともできる。
自分の特性を理解しながら、自分に合った働き方を選び、自分にとって息のしやすい人間関係を築いていく。
「困らせる社会」を無理に生き抜くのではなく、自分らしさが発揮できる場所を“選んで”いく自由。
それもまた、ニューロダイバーシティが伝えたい本質のひとつなのだと思います。
極論を言えば、「どんな社会を生きるか」は、ある程度自分で選べる時代になってきました。その選択には勇気がいるかもしれないけれど、「あなたを困らせる環境」から、「あなたが活きる環境」へと動くことはできます。
「障害」や「特性」をめぐる話は、社会モデルと個人モデルのどちらか一方ではなく、どちらの視点も持ちながら、自分の人生をデザインしていくことが大切だと思っています。
6. ラベルに縛られないために。診断名は取扱説明書であってもいい
「発達障害」という言葉が可能性を閉じ込めることがある
「発達障害」という診断名は、確かに本人や家族が支援につながるための大切な手がかりになります。実際、多くの人が診断を通して自分を理解し、必要な支援につながるきっかけを得ています。何より異質な何かっていうより、診断名が付くことは安心できますし。
しかし一方で、そのラベルが人の可能性を狭めてしまうリスクも潜んでいると思います。たとえば、こんな思い込みにとらわれていないでしょうか?
- 「ADHDだから忘れっぽい。だから仕事は無理」
- 「ASDだから人付き合いができない。だからチームでは働けない」
こうした思考は、「診断名=制限」ととらえてしまう典型的な例です。
でも、視点を少し変えてみるとどうでしょう?
- 「空気が読めない」→「嘘がつけない、誠実で正直な表現者」
- 「多動」→「行動力とエネルギーにあふれた人」
- 「過集中」→「ひとつのことに深く没頭できる力」
同じ特性でも、言葉の捉え方ひとつで“弱み”は“強み”に変わるのです。
ラベルの裏には、まだ言葉になっていない才能が眠っているのかもしれません。これは本当にそうだと思っています。
「違い」は、過去の天才たちも持っていた
歴史を振り返ってみても、「違い」を強みに変えた人はたくさんいます。
たとえばレオナルド・ダ・ヴィンチ。
彼は複数の分野に同時に興味を持ち、絵画、科学、工学、解剖学など、ジャンルを超えて探究し続けた人物です。
一方で、アイデアが次々と湧きすぎて、作品を未完のまま残すことも多く、現代の視点で見れば、ADHD的な特性や過集中の傾向を持っていたとも言われています。
けれど、だからこそ彼は「誰にも真似できない好奇心と集中力」を武器にし、ルネサンス期最大の天才として名を残しました。
アルベルト・アインシュタインも、幼少期は言葉の発達が遅く、「学習障害ではないか」と心配されたことがあるそうです。
けれど、彼独自の“視覚的・空間的な思考”こそが、後に相対性理論という革新的な概念を生む源になったのです。
つまり、人と違う脳の使い方が、「世界の見え方そのものを変えてしまった」例が、すでにいくつも存在するのです。
「ラベル=限界」ではなく、「ラベル=取扱説明書」
診断名やラベルは、「あなたはこういう人です」と決めつけるものではありません。
むしろそれは、「自分を理解するヒント」 「よりよく生きるための設計図」として使うことができます。
僕の知人で、ADHDと診断されたあと、しばらく自信をなくしていた人がいます。「やっぱり自分はどこか欠けているんだ」と思い込んでしまったのです。
でもある日、ふとこう考えたそうです。「これはダメな自分を示す証拠じゃなくて、自分の取扱説明書かもしれない」
そこから、彼は少しずつ環境を整えていきました。
- 忘れっぽさを補うためのメモ習慣を徹底する
- 興味のあることに特化して集中力を活かす
- 一人で動ける働き方にシフトする
その結果、今ではフリーランスとして自信を持って働き、日々を楽しんでいます。
つまり、ラベルは、あなたを縛るものではなく、あなたを理解するためのツールになりうるのです。
それを「壁」にするのか、「道しるべ」にするのか。 その選択権は、いつもあなたにあります。
言葉の力を、可能性を広げるために使う
僕たちは、言葉で世界を理解し、言葉で自分を語ります。
だからこそ、「どんな言葉で自分を語るか」は、とても大切なのです。
- 「自分はHSPだから無理」ではなく、「繊細さを活かせる環境で生きよう」と言ってみる。
- 「ASDだから苦手」ではなく、「このやり方ならできるかもしれない」と工夫してみる。
ラベルをどう使うかは、あなたが選べます。
言葉は、傷を広げることもできれば、癒す力にもなります。
「あなたが自分にかける言葉」は、あなた自身の未来を静かに形づくっていくのです。ニューロダイバーシティの本質は、「違いを否定せずに受け入れること」
つまり、「みんな同じが当たり前の世界」から「みんな違うのが当たり前の世界」へパラダイムシフトです。
そしてその第一歩は、「言葉の選び方」を変えることから始まるのかもしれません。言葉は、可能性を閉じるナイフにも、可能性を開く鍵にもなる。
あなたは、どんな言葉で自分を語っていきたいですか?
7. 「支援=特別」じゃない。社会全体をアップデートする視点
支援は進化
火を使うことで食べ物の衛生が守られ、文字を生み出すことで知識を共有できるようになり、道具を発明することで、「できなかったこと」が「できること」に変わってきました。
そう、人類の進化はいつも、「足りないこと」や「できなかったこと」をきっかけに始まってきました。そこに知恵や工夫を加えることで、新しい可能性が次々と生まれてきたのです。
そして現代に目を向けてみると、私たちが日常で使っている便利な技術やサービスの多くも、実は「誰かの生きづらさ」から生まれた支援のアイデアでした。
「支援」がみんなの便利に進化した例
- 字幕:もともとは聴覚障害のある人のため → 今では電車の中やカフェでの動画視聴に欠かせない
- 音声入力:手が使えない人のため → スマホや車内ナビ、料理中のメモにも活用
- 在宅勤務:通勤が難しい人のため → 働き方改革の象徴として社会に浸透
最初は「特別な誰かを支えるため」に生まれた技術が、いまや誰もが便利に使うものに変わっています
支援は、ネガティブな意味のやさしさではなく、進化の発明。それは、社会全体をより柔軟に、クリエイティブに変えていく力を持っています。
企業も「違い」を武器に変えている
最近では、「ニューロダイバーシティ」を取り入れ、多様な脳の特性を活かす企業も増えてきました。
- マイクロソフト:自閉症スペクトラムの人の特性に合わせた採用プログラムを実施。面接や職場環境も最適化し、イノベーションの源に。
- SAP:「Autism at Work」プログラムで、自閉症の人材をソフトウェアテストなどで活用。高い集中力と注意力を評価。
- 凸版印刷:「SLOW LABEL」プロジェクトを通じて、発達障害のあるクリエイターの感性をプロダクトに活かす。
- アクサ生命保険:「チャリティではなくチャンス」の理念で、多様な特性を持つ社員を積極的に登用し、意義ある仕事を提供。
これらの企業は、支援を特別かつ合理的な配慮ではなく、新しい価値創造のきっかけと捉えています。
ユニバーサルデザインの本質は「違いがある前提」でつくること
“ユニバーサルデザイン”という考え方があります。それは、「特別な人に後から対応する」のではなく、最初からみんなの違いを前提に設計するという思想です。
たとえば:
- 車椅子でも通れるスロープや広い通路
- 見やすさに配慮した色使いやフォント
- 年齢や能力に関係なく使える、直感的なUI(ユーザーインターフェース)
これらはすべて、「一部の人のため」ではなく、すべての人にとって快適なデザインとして社会に馴染んでいます。
そしてこれは、建築や道具だけに限った話ではありません。
教育、働き方、公共サービスなどなど。あらゆる仕組みが「違いのある人たちを前提」にして設計し直せるのです。
社会全体がユニバーサルになったら、何が変わる?
想像してみてください。
もし、制度やサービス、働き方や教育が「多様な人がいる前提」でつくられていたらどうでしょう?
「特別な支援」が目立つことはなくなり誰かが無理に“合わせる”必要もなくなりすべての人が、自分らしく自然体で過ごせる社会が生まれます。
支援とは、「誰かのため」ではなく「みんなのための再設計」。それはやさしさや配慮ではなく、未来のスタンダードをつくるデザインなのです。
支援とは、進化のアイデアである
支援とは、「誰かの弱さを補う」ためのものではありません。
それは、人間が「より自由に、より快適に」生きるための進化の装置です。
誰か一人のどうしよう?という声を出発点に、みんなが使える便利な仕組みが生まれる。
この発想こそが、ニューロダイバーシティの本質であり、未来の社会をアップグレードするための架け橋になるのではないでしょうか。
8. 人間は似ていなくて当たり前。ニューロダイバーシティの原点に還る
Jane Meyerding のエッセイが教えてくれること
前述しましたが、「ニューロダイバーシティ(Neurodiversity)」という言葉が広く知られるようになったのは1990年代後半。その原点のひとつが、1998年に書かれた Jane Meyerding(ジェーン・メイヤーディング)のエッセイにあります。
彼女は自閉スペクトラム(ASD)の当事者として、こう語っています。
「私たちは、“違いをなくす社会”ではなく、“違いを前提にした社会”を目指すべきだ。」
この一文は、ニューロダイバーシティという概念の真髄を端的に表しています。
「人間は、似ていなくて当たり前」それを社会のスタートラインにできたら、どれだけの人が生きやすくなるでしょうか。
「違いがあることを“受け入れる”」のではなく、「最初から違いを前提にする」。この発想の転換こそが、真に多様な社会の始まりです。
平均値を目指す時代から、「分布の広がりを活かす」時代へ
これまでの社会は、「平均」に近づくことがわりと“正解”とされてきました。
- 学力テストで平均点を取ること
- 一般的な働き方や生活パターンに適応すること
- 多数派に同調できること
でも、自然界に目を向けてみると、その価値観の偏りに気づきます。
- 花の色がすべて同じだったら、どれほど味気ないでしょう?
- 動物がすべて同じ大きさ・性格だったら、自然の調和は成り立つでしょうか?
多様性は、“あってもいい”のではなく、“あってこそ”面白いものなんですよ。
人間もまた、自然の一部です。
だから、神経的な違い=脳の多様性があるのは、むしろごく自然で当然のことなのです。
そして、これからの社会は「平均」や「同調」を求めるのではなく、それぞれの違いの“分布の広がり”そのものを活かす時代へとシフトしています。
ニューロダイバーシティは、「あなたがあなたであること」の肯定
この概念は、医療や教育の枠にとどまるものではありません。
それはむしろ、「人間の見方そのもの」を静かにひっくり返す哲学だと思っています。
- あなたが他人と違っていても、それは間違いではない
- あなたの感じ方や考え方には、ちゃんと意味がある
- あなたが「この世界で浮いている」と感じるとき、それはあなたが間違っている証”ではない
ニューロダイバーシティとは、「あなたがあなたであっていい」とそっと背中を押してくれる、人生の見方なのです。
そしてそれは、他者に対しても同じことが言えます。
「この人は、自分と違っていて当たり前」そう思えたとき、比較やジャッジメントのない優しい人間関係が生まれ、社会の空気も変わっていくはずです。
違いを受け入れるということは、単に「我慢すること」でも「許すこと」でもありません。
それは、世界をもっとクリエイティブに、自由にしていく選択なのです。
ニューロダイバーシティは、あなたの違いを尊重すべき美しさとして見るためのレンズです。
そしてそのレンズを通して世界を見たとき、これまでとまったく違う光景が、あなたの目の前に広がりはじめるでしょう。
次章では、「ニューロダイバーシティ的に生きる」とは実際どういうことか? 日常のヒントとともに、具体的に探っていきましょう。
9. ニューロダイバーシティ的に生きるとは? あなたの違いが強みになる瞬間
あなたの「違い」は、あなたの強みになる
もし、「みんなと同じ」であることが正解だと信じていたら、ほんの少しでも人と違う自分を「欠けている」と感じてしまいます。
でも、ここまで読んでくださったあなたは、きっともう気づいているはずです。
その“違い”こそが、あなたの唯一無二の強みになりうるのです。
たとえば
- 忘れっぽいけど、アイデアは無限に湧いてくる
- 集団が苦手だけど、ひとりでの作業に没頭できる力がある
- 言葉にするのが苦手だけど、感覚で人の気持ちを深く受け取れる
- ミスが多いけれど、小さな違和感にいち早く気づける
- 作業が遅いけれど、一つひとつを丁寧に仕上げる誠実さがある
こうした「苦手」とされている部分のすぐ隣には、あなたにしかない才能の芽が静かに眠っています。
「違い」は劣っているのではなく、ただの“仕様の違い”。あなたという存在は、この世界にとって“ユニークなピース”です。それを欠陥ではなく、かけがえのない個性として抱きしめてください。
「適応するか、適応させるか」ではなく、「選ぶ」という生き方
長いあいだ、僕たちは「社会にどれだけ適応できるか」で自分の価値を測ってきました。
- 朝が苦手なら「ダメなやつ」
- 空気を読めなければ「空気が読めない人」
- 同じスピードで動けなければ「遅れてる人」
でも、これからはその常識をそっと横に置いてみましょう。
「自分に合う生き方を、自分で“選ぶ”」ことが、これからの時代のスタンダードです。
たとえば
- 朝が苦手? → 夜型の働き方を選ぶ
- 集団が苦手? → フリーランスや在宅ワークという道を探る
- 一つのことに集中したい? → マルチタスクを避ける環境を選ぶ
テクノロジーの発達や働き方の多様化は、 「みんなに合わせる時代」から「自分に合った生き方をデザインする時代」へと変わりつつあります。
もちろん、今すぐすべてを変えることは難しいかもしれません。 でも、「選べる可能性がある」と知るだけで、
あなたの“心の自由度”は、大きく変わるはずです。
自分のリズムに合った世界を選んでいい
社会に自分を合わせることが美徳とされてきた時代。
でも、ニューロダイバーシティ的な生き方は、こう語りかけてくれます。「あなたは、自分のリズムに合った世界を選んでいい」
誰かと比べなくていい。 無理に“普通”にならなくていい。
そして何よりその選択は、“誰かのため”ではなく、“あなた自身のため”にしていいのです。
ニューロダイバーシティは、単なる概念ではなく、「あなたが自分を大切にしていい」と許可してくれる、生き方そのものなのです。
他の誰かになる必要はありません。 ただ、あなたがあなたを心地よく生きられるリズムを見つけてあげるだけでいいのです。
そのリズムに合う世界は、探せばきっと、どこかにあります。 いや、あなたが生きることで、その世界は“今ここ”から始まるのかもしれません。
10. あなたの“普通”を再定義する。 違いを愛するという生き方
「違いがある」ことは、ようやくスタートラインになる
今、社会では「多様性が大事だ」と繰り返されるようになりました。 「個性を尊重しよう」「みんな違っていい」。
でも、そこにはまだどこか、“特別扱い”の空気が残っていないでしょうか? 「違う人がいても仕方ない」「理解してあげよう」そう言っているうちは、 本当の意味で「違いを前提にする社会」にはなっていないのかもしれません。
多様性とは、「許す」ことではなく、「最初から違うことを前提にしている」状態のことです。
誰かが後から「配慮」されるのではなく、 みんなが「自分らしくいられる設計」が、社会の初期設定になる。 それが、これからの理想的な社会のあり方だと、僕は思っています。
違っていることは、恥でも、失敗でも、弱点でもありません。
それは、あなたがこれから歩いていく人生の“オリジナルな地図”です。
「あなたにとっての“普通”は、誰が決めたのか?」
「普通に働かなきゃ」 「普通に話さなきゃ」 「普通に生きなきゃ」
そんなふうに、自分を“普通”という型に押し込めようとしていませんか? でも、その「普通」って、いったい誰が決めたのでしょう?
僕たちは、生まれた瞬間からみんな違っていたはずです。 感覚も、思考のスピードも、得意なことも、苦手なことも、 一人ひとり違っているのが、当たり前だったはずです。
もし「普通」という言葉がこの世から消えたとしたら── あなたはもっと自由に、自分らしく、生きられるのではないでしょうか?
「普通」は、安心感ではなく、あなたを縛る無意識のルールかもしれません。
たとえば、朝がつらい日はゆっくり始めてもいい。
大勢と話すのが苦手なら、静かな空間を選んでもいい。
自分の得意なやり方を見つけて、それを大切にしてもいいんです。
あなたの「違い」が、世界にスパイスを
人は、長い間「人と違うこと」を恥じるように教育されてきました。 でも、よく考えてみてください。
社会に“新しい風”を吹かせてきたのは、いつも「違い」から始まったアイデアでした。
- 今までにない視点
- 誰も思いつかなかった方法
- 周囲と合わない感性
それらこそが、世界を前に進める原動力になってきたのです。
あなたの違いは、誰かの生きづらさを癒す鍵になるかもしれません。 あなたの違いは、これからの時代をつくっていく“素材”になるかもしれません。
だからこそ、こう伝えたいのです。
「違っているあなたがいるから、この世界は面白い。」
最後に──「違いを愛する」という生き方
僕がヒーリングという世界に出会ってから、何より大きかったのは、 「自分はこのままでいい」と思えるようになったことでした。
それは、自己啓発でも、自己肯定感のトレーニングでもなく、 もっと静かで、深くて、やさしい感覚です。
あなたの違いは、あなたが持って生まれた「ギフト」です。
- それを受け入れて、愛すること。
- そして、他人の違いにもやさしくなれること。
それこそが、ニューロダイバーシティ的に生きるということなのかもしれません。
自分の違いを受け入れるということは、
人生の静かな中心に還る旅かもしれません。
もしあなたが、もっと自分を知りたいと思ったら── そっと深呼吸して、静かに心を見つめる時間を持ってみてください。
それは、あなたの本質と再会する大切な一歩です。
あなたが自分を大切にすることは、世界が少しやさしくなること。
この文章が、そんな未来の小さな一歩になってくれたらうれしいです。 読んでくださって、本当にありがとうございました
ここまで読んでくださって、「もっと自分のことを知ってみたい」「違いを強みにできる感覚を体験してみたい」と感じた方へ。
僕は普段、シータヒーリングという手法を使った個人セッションや、自己理解を深める講座を提供しています。
静かに心を見つめたいとき、自分らしさにもう一度つながりたいときに、そっと寄り添える時間になれたらうれしいです。
▶︎ 体験セッションの詳細はこちら
▶︎ シータヒーリング講座のご案内はこちら
。
11. もっと学びたい人へ|ニューロダイバーシティおすすめ本とサイト
この記事を読んで、「もっと深く知りたい」「他の人の視点も見てみたい」「自分にできることを考えたい」と感じてくれた方へ。
ここでは、読者の立場や関心に合わせて、役立つリンクと書籍を厳選してご紹介します。
あなたの「知りたい」に、ぴったりの入り口が見つかりますように。
A. 初めてニューロダイバーシティに触れた人へ(初心者向け)
「そもそもNDってなに?」「どんな背景があるの?」という人におすすめ
📚 書籍
- 『ニューロダイバーシティの教科書: 多様性尊重社会へのキーワード』村中直人
▶︎ Amazonリンク
やさしい言葉でNDの基本と、社会の見方を変える視点を届けてくれる一冊。 - 『脳には妙なクセがある』池谷裕二
▶︎ Amazonリンク
脳の個性って面白い!と感じられる科学×日常の名著。
🔗 Web
B. 当事者・グレーゾーンの人へ
📚 書籍
- 『発達障害「グレーゾーン」』岡田尊司
▶︎ Amazon - 『発達障害からニューロダイバーシティへ ポリヴェーガル理論で解き明かす子どもの心と行動』モナ・デラフーク
▶︎ Amazon - 『ニューロダイバーシティと発達障害、天才はなぜ生まれるのか』正高信男
▶︎ Amazon
🔗 Webサイト
C. 支援者・教育関係者・企業の人事担当者へ
📚 書籍
🔗 企業の取り組み・制度紹介